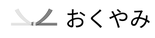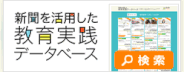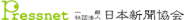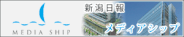【「戦争をしない」を続けるために 戦後80年座談会第3回「経済と政策決定」】
あの戦争を、どこでとめることができたのでしょうか。委員会「戦後80年--『戦争をしない』を続けるために」の座談会3回目のテーマは、「経済と政策決定」です。
慶応大の牧野邦昭教授が、第一次世界大戦からの日本の歴史を振り返り、昭和恐慌や日中関係の悪化、2・26事件をひもときながら、日米開戦に突き進んだ経緯を基調報告しています。「正しい情報があることと、正しい選択が行われることは違う」。そんな問いかけとともに、「開戦を正当化するため、都合のいい情報を取捨選択した。希望的観測に基づき太平洋戦争に進んだというのが経済的に見た日米開戦だ」と論じています。
この報告をベースに、日中・日英米の戦争を決断した政策決定がどのように進んだのかを話し合いました。学習院大の井上寿一教授や元岩手県知事で元総務相の増田寛也氏、東京大の小泉悠准教授、作家の温又柔氏、政策研究大学院大の岩間陽子氏が座談会で、じっくりと意見を交わしました。当時と現代の国際社会における経済的な類似性を深く考察し、戦争をしないために必要なことは何か。日米開戦の教訓を現代にどう生かすのか。示唆に富む議論が展開されています。(見開きの特集面)。

 NIC今町
有限会社 角田新聞店
NIC今町
有限会社 角田新聞店